
「ただいまー!書類忘れちゃった~」
ドアを勢いよく開けながら、私はヒールを脱ぎ捨てた。普段ならこの時間、家には誰もいないはず。だからこそ、リビングでスーツ姿の義兄が弁当を広げているのを見て、ハンドバッグを落としそうになった。
「菫…?こんな時間にどうした?」
そう言いながら、義兄の視線が私の服装を舐め回す。ノースリーブのブラウスから覗く肩、タイトなスカートで強調された腰のくびれ。営業用のいつもの格好だけど、家族の前では確かにやりすぎかも。
「あ、あはは…営業でーす!お兄ちゃん、今日はお休み?」
「在宅勤務だ。…それで、その格好で?」
義兄の眉間に皺が寄る。その反応が妙に嬉しくて、私はふざけてソファにドスンと座り込んだ。
「どう?似合うでしょ~。ねぇお兄ちゃん、私のこの鎖骨、めっちゃ綺麗って同僚に言われたんだよ?」
「…ふざけるな」
「え~?でも先週、飲み会でお兄ちゃんも聞いたじゃん。私が『喉の奥まで舐められるのたまんない』って言ってるの」
その瞬間、空気が凍りついた。義兄の手が箸をギュッと握りしめ、関節が白くなる。まずい…流石にやりすぎたかも。本気で怒られる覚悟で目を閉じた。
「…あの話、本当か?」
低く震えた声。びっくりして目を開けると、義兄の目が真っ直ぐに私を見つめている。11年間、一度も見たことない表情だった。
「え?あ、その…」
「答えろ。本当に…そんなこと考えていたのか?」
胸が高鳴る。この機会を逃したら二度とない。そう直感した私は、震える手でスカートの裾を握りしめた。
「だって…だってお兄ちゃんのこと…!」
溢れ出した涙が、つけまつげを濡らす。頬を伝わる黒い筋。義兄の顔が一瞬歪んだ。
「…馬鹿め」
次の瞬間、強い力でソファに押し倒された。後頭部を掴まれ、義兄の膝の上に頭を乗せられる。
「『家族』の前でそんな言葉を吐くとは…罰が必要だな」
「や…お兄ちゃ…んっ…!?」
口を塞がれた。義兄の指が、いきなり喉奥まで突き入ってくる。吐き気が込み上げて、私は必死にその手首をつかんだ。
「がほ…っ!げほっ…!」
「これが欲しかんだろう?汚らわしい…」
べとついた指が口から引き抜かれると、今度は頬に叩きつけられた。唾液の糸が切れて、スーツの裾に落ちる。
「お兄ちゃん…ひどいよ…」
「自分で言ったことだろう?」
ネクタイが外れる音。瞬く間に手首を縛られ、頭髪を掴まれる。開いた口に、義兄の怒張したものが押し込まれてきた。
「んぐっ!?んんっ!!」
涙が溢れる。メイクがさらに崩れる。それでも喉の奥を犯される快感に、腰が浮き上がる。11年間の想いが、痛みと快楽に変換されていく。
「家族だろう?しっかり…飲み込め」
「んぐ…っ!ごくっ…んん…!」
奥まで押し込まれる度に、胃が痙攣する。でも、私は精一杯舌を動かした。だってこれが…本当に欲しかんだったから。
「…っ!お前は本当に…」
義兄の声が初めて乱れた。ネクタイで縛られた私の手首を掴み、激しい動きが始まる。喉の粘膜が擦れる音が響く。
「んんっ!んぐ…ごくっ!」
涙と鼻水と唾液でぐしゃぐしゃになりながら、私は必死に飲み込んだ。仏壇に飾られた母の写真が、ちらりと視界に入る。
「…っ!出る…」
「んんっ!!」
熱いものが喉奥に注がれる瞬間、私は初めて義兄の手の震えに気付いた。ゆっくりと口から抜かれると、ぐったりとソファに倒れ込んだ。
「…二度とするな」
そう言い捨てて立ち去る義兄の背中も、微かに震えていた。
翌日から、義兄はわざと帰宅時間をずらすようになった。でも1週間後、私は玄関で待ち伏せした。握りしめたネクタイに、まだあの日の匂いが残っていたから。
「今度は…お兄ちゃんの分も、全部受け止めてあげる」





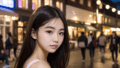

コメント