
「もうっ! 悠真ったら最悪!」
23歳の亜美はスマホをバンッとベッドに投げつけた。同い年の彼氏の悠真とは付き合って1年半。最近ちょっとマンネリ気味で、今日だってデートの約束をドタキャンされたんだから。
「仕事忙しいって…それって本当なの? 最近ラインの返事も遅いし…」
部屋で一人悶々としていると、スマホが震えた。悠真からの着信だ。
「…もしもし」
「亜美、今どこ? 俺、君のマンションの前なんだけど」
ビックリして窓の外を見下ろすと、確かに悠真が立っている。ちょっとイケメン過ぎるその顔が、こっちを見上げてニヤリと笑った。
「ちょ、なんでいきなり…!」
「さっきの電話、ごめん。実はサプライズ用意してたんだ」
階段を駆け下りてエントランスへ飛び出した亜美は、悠真の胸に飛び込んだ。
「ひどいよ…心配させて…」
「ごめんごめん。でも、今日は特別な日だろ?」
そう言われてハッとした。今日は二人が初めて結ばれた記念日だった。
悠真の手には高級レストランの予約確認メールが表示されたスマホと、小さな箱が。
「まさか…プロポーズ…?」
「それはまだナイショ。とりあえず、ご飯食べに行こう」
レストランでのディナーは至福の時間。ワイングラスを傾けながら、あの日のことを思い出す。
「悠真って、あの時めっちゃ緊張してたよね」
「そりゃあ、好きな子と初めてだもん。でも亜美の方が震えてたぞ」
「うっさい! だって…あの時の悠真、普段と違ってめっちゃ攻めだったんだもん」
ほろ酔い気分でマンションに戻ると、エレベーターの中で悠真が急に亜美を壁に押し付けた。
「…今日も攻めだった?」
「ちょ、エレベーターの中じゃ…んっ!」
遮る言葉を飲み込むように熱いキス。悠真の舌が乱暴に侵入してきて、亜美は膝がガクガクするのを感じた。
「はぁ…悠真、ダメ…まだ玄関も…んんっ!」
ドアを開けるやいなや、服を脱がされながら寝室へと押し倒される。亜美のブラウスはあっという間に床に落ち、真っ白な肌が露わに。
「あの日みたいに…亜美を全部味わいたいんだ」
悠真の手がブラのフロントを外すと、ピンク色の先端がすでに硬くなっている。
「あっ…やだ、そんなに見ないで…んぁ!」
舌で舐め上げられ、亜美の体はびくんと跳ねた。もう1年半も付き合っているのに、毎回初めてみたいにドキドキする。
「悠真の舌…熱い…あ、そこっ…すごい…」
リビングまで続く喘ぎ声を気にしながらも、快感に身を任せる。悠真の指がパンティの中に滑り込み、じっとりと濡れた秘所を探る。
「もう…こんなに濡れてるじゃん」
「うん…だって、悠真と…したくて…」
パンティを脱がされ、亜美は悠真のズボンのチャックを開ける。中から飛び出したのは、すでに先端から汁を滲ませた立派な男根。
「今日は…あの日みたいに激しくしてほしい」
「分かってる。亜美がイくまで、何度も…」
腰を押し付けられ、一気に貫かれる。
「あぁっ! んんっ…入、入りすぎ…」
何度も経験しているのに、毎回最初はきつくてたまらない。でも、その苦しさが次第に快感に変わっていくのを亜美は知っている。
「亜美の中…めっちゃ熱いよ」
「んあっ…動いて…もっと…」
激しいピストンが始まり、ベッドがきしむ。悠真の腰使いは今日は特に荒く、亜美は何度も頭を揺らしながら絶頂へと追い込まれていく。
「もう…イッちゃう…一緒に…んああっ!」
深く突き上げられ、二人は同時に頂点へ。熱いものが体中に広がっていくのを感じながら、亜美は悠真の首にしがみついた。
「…絶対許さないからね」
「え?」
「今日みたいにサプライズするなら…次は私が主導権取るから」
そう囁くと、悠真は楽しそうに笑った。
「それも悪くないな。じゃあ、次は亜美に縛られようかな」
「ま、まさか…私がSって…?」
照れくさそうに顔を赤らめる亜美を見て、悠真は再び体を重ねた。
「これからも、ずっと色々試そうぜ」
「…バカ」
そう言いながらも、亜美の足は自然と悠真の腰に絡みついていた。






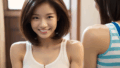
コメント