
朝もやが立ち込める5時半、私はリビングのソファでぐっすり眠っているはずの義兄・悠真のことを考えていた。25歳の彼には婚約者がいて、その彩夏さんという女性が最近家に泊まりに来ている。23歳の私は大学生で、普段は寮で暮らしているけど、今は実家に帰省中。
「柚乃ちゃん、起きてたの?」
彩夏さんの声にびくっとした。キッチンからコーヒーの香りが漂ってくる。彼女は悠真の好みを全部知っているみたいで、毎朝彼のために丁寧にドリップコーヒーを作っている。
「あ、うん…ちょっと眠れなくて」
私が答えると、彩夏さんはにっこり笑った。
「悠真くん、柚乃ちゃんのことすごく可愛がってるよね。妹想いでいいなあ」
その言葉が、なぜか胸に刺さった。私は下を向いて、テーブルクロスの端をぐしゃぐしゃと握りしめる。
ふと外を見ると、庭に人影が。彩夏さんには見えない位置で、見知らぬ男性が立っていた。30歳くらいだろうか、スーツ姿で整った顔立ちの男性が、じっと私を見つめている。
好奇心に駆られて庭に出ると、男性が静かに話しかけてきた。
「君が柚乃さんか。彩夏の…いや、何でもない」
彼の冷たい指が私の顎を撫でた。鳥肌が立つのがわかった。
「彩夏さんの…?」
聞き返そうとした瞬間、男性は私の口を手で塞ぎ、物置の方へと引きずり込んだ。
「静かにしろ。彩夏には内緒だ」
薄暗い物置で、彼の手が私の制服のブラウスに伸びた。抵抗しようとしたけど、なぜか体が動かない。
「お前、悠真のことが好きだろ? 兄さんを困らせてみたいとは思わないか?」
その言葉で、私ははっとした。バレてたんだ…
男性の手が私のスカートの中に入る。冷たい指がパンティーの上から陰部を撫でて、思わず声が漏れそうになる。
「ほら、こんなに濡れてる。お前も望んでるんだろ?」
耳元で囁かれて、腰が浮いてしまった。
突然物置のドアが開き、眩しい光が差し込んだ。
「柚乃!何してるんだ!?」
悠真の怒鳴り声が響いた。男性はさっと私から離れ、影に消えていった。
涙が止まらなかった。悠真が私を抱きしめてくれるのを待っていたのに、彼はただ呆然と立ち尽くしていた。
「だめだ…もうだめだよ、兄ちゃん…」
私の嗚咽が、朝もやの中に消えていった。






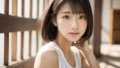
コメント